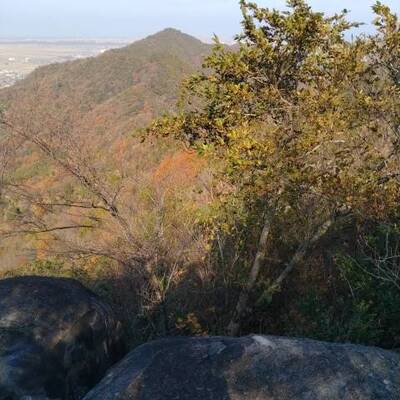歴史の山「虎御前山」
UPDATE 2026-02-16
【日 程】 2026/02/14(土)
【参加者】 会員8名
【コース】 河毛駅―山脇山―岡山―虎御前山―虎姫駅
【記 者】 kangetu
車窓から眺める穏やかな田園風景に「ああ~雪がない」。低山でも、この地なら雪があると期待していたが、仕方がないと思い直す。
河毛駅前に建つ浅井長政とお市の方の像の前に、ボランティア活動をされている方がおられ、「よく来ていただいた」と言葉をかけていただく。そして、「ここは、山本山・賤ヶ岳、小谷山が一度に見える場所だ」と教えてもらい、今から行くコース説明も受けて、さあ、スタート。
山脇山(明智光秀陣所跡)から岡山に登る。ここには、小谷城防衛のために建てられた城、丁野山城跡・中島城跡がある。小さな堀切や犬走りなどが残っており、タイムスリップ。整備されているのでコースも歩きやすい。
次に目指すは、虎御前山。南北一直線に伸びる尾根の山で、織田信長が小谷城を攻めるために陣を置いた山である。最初こそ急登であったがそこを過ぎると、小さなアップダウンの繰り返しはあるものの、ふかふか絨毯の上を歩く快適な登山道。東を見れば小谷山・雪の伊吹山、西には琵琶湖や竹生島が一望できる。青空ならもっとよかっただろうが。 歩き進めると、秀吉や信長をはじめいくつかの陣所跡、横堀・竪堀、土塁や犬走りなどが残っている。また、木々に覆われているので、自然の要塞になっていたのだろう。歴史の山であることを実感。 NTT鉄塔から展望台、続いて矢合神社の大きな石鳥居をくぐって車道へ出ると、私たちを待っていたかのようにかき集められた雪の山。「わぁあ~雪や」しっかり踏みしめて、虎姫駅へと向かった。
春のような日差しの中、ゆっくりと歴史の足跡を辿る山歩きができた。心残りとなった雪遊びをする機会が、またいつかあればいいのだが。
今回は半周、次回は一周 〜余呉トレイル〜
UPDATE 2026-02-04
【日 程】 2026/01/31(土)
【参加者】 7名
【コース】 余呉駅ー賤ヶ岳登山口ー岩崎山ー賤ヶ岳ー分岐ー余呉湖畔駐車場ー余呉駅
【記 者】 S.N
1月下旬の寒波襲来のおかげ?で、雪に恵まれた余呉トレイル。往復JR利用予定だったので、前日の倒木による長浜〜近江塩津間運転取り止めにはヤキモキ。それも夕方には復旧しヤレヤレ。無事当日を迎えられワクワク。
9時前、余呉駅に到着。辺り一面銀世界。ホームにも雪の山!初めて見る光景にビックリ!改めて雪の多さを実感する。駅から登山口までの車道脇にも雪の山。車に気をつけながらも歩くのに難儀する。
民家の間から始まる賤ヶ岳への登山口を9時半スタート。70〜80cmは積もっているであろう雪の中、しっかりトレースがついていて歩きやすい道。ワカン、スノーシューも必要ない。
今回の計画では、余呉湖を一周する予定だったが、雪の多さと、帰りの電車時刻との兼ね合いから、今回は公法寺山手前から車道に下りようと予定変更。時間に余裕ができたので、途中立ち寄った岩崎山でワカン装着、しばし雪を楽しむ。
再びトレース道に戻り、一旦ワカン終了。賤ヶ岳山頂目指して足を進める。
山頂到着12時20分。この日の天気は曇り時々雪。山頂の気温は1度もない。風もきつく、寒い寒い。しかし、ここからの琵琶湖と余呉湖を同時に楽しめる、この雪景色を私は見たかった!展望台からのんびりというわけにはいかないが、お昼休憩を取りつつ、この景色に見入っていた。
賤ヶ岳から公法寺山方向へ再び進む。予定変更のルート分岐から少し登ったあたりで、この雪を目の前にして、このままワカン履かずに帰れるか!とばかりに、本日2度目のワカン装着。各々好きに雪と戯れ、ワカンのまま下山。予定の電車にも無事乗車。
今回は半周で終わった余呉トレイル。一周回り切る宿題はいつかやりましょう、ぜひ!
ずいぶん雪が少ないなぁ 鈴鹿/鈴北岳
UPDATE 2026-01-19
【日 程】 2026/01/18(日)
【参加者】 5名
【コース】 大君ヶ畑登山口-茶野-鈴ヶ岳-鈴北岳-鞍掛峠-大君ヶ畑登山口
【記 者】 里山
今回のコースは、歩いた経験があるコースだった。なので最初に感じたのは、「Y師匠が、昨シーズンにワカンの練習をした仲間に向けて、計画を立ててくれたのだな。」ということだった。少々距離は長いが、ワカン初級者の練習にはもってこいな場所。(ただし、適正な指導係がいる場合に限る) 「こりゃ、参加でしょ!」と参加を決める。後日、参加メンバーの顔触れを見て怖気づく。「えェーっ⁉、男性ばっかりジャン⁉」「私、足手まといでしょ⤵」「いやいや、みんなにラッセルしてもらって、楽ちんだあ⤴」交錯する気分を抑え込んで、当日参加。
登山口についてみると雪が少なそうなので、みんなで協議。今回のメンバーは、積雪30㎝くらいなら【つぼ足】で歩けるメンバー。持参したワカンは荷物になるので、車に置いていく事にする。(岩場もなく雪の表面が凍結する時季でもないので、そもそも選択肢にアイゼンはない)
稜線までの登りは雪が全くなく、登山道に吹き溜まった雪に苦戦しながら登るはずだったのに、落ち葉踏み踏み秋山登山。私に多少は合わせてくれるものの、スピードが上がって心臓破りの登りとなる。
標高が高くなると多少雪があり、山の斜面の向きによっては、ラッセルできる雪。稜線をいくつかのピークを上り下りしながら進む。途中、休憩を兼ねて勉強会。今回のメンバーには遭難捜索現場をよく知る人が二人。冬枯れの木々、下草は雪の下、広くまあるくて見通しの良い尾根の上。実は、道迷い遭難が起こりやすい地形であるので、地図と実際の風景を合わせつつ、遭難例を参考にレクチャー。説明を受けてもなかなかピンとこない生徒たち。とても難しいんです。でも「いつか何かの折にきっと彼ら自身を助ける力になる」と信じて丁寧に教えてくれる先輩たち。
道迷いをしないのがまず第一。そのために日々勉強をしているのだけれど、どんな名人だってミスをする。とすれば、「変だな???」と思った時どうするか。よく、【山で迷ったら下るな。谷に向かえば滑落する危険が待っているから。】と言われるけれど、疲れた体が少しでも楽な下りに向かって進むのは想像に難くない。
そこで、Y師匠が教えてくれたシンプルな動作。「迷ったら立ち止まって、みぎひだりを見て、周りで一番高い方向に行け。」高いとこに行けば見通しがよくなって、道を見つけられる可能性が上がるから。念仏のように唱えながら、一歩一歩進むことを覚えておきます。
お天気が良く、仲間の先行ラッセルに助けられて、気持ちよく鈴北岳へ到着。続いて鞍掛峠へ向かっての下り。広い尾根なので尾根の中心を歩けば滑落の心配はない。北側の斜面なので存分の雪。【つぼ足】の我々、下ろす一歩一歩が膝下くらいまで埋まる。傾斜角度はそこそこあるので、止まらずに次の足を出すのがベター。かくて、急きょ、腿上げ徒競走開幕!下りだけれど、しっかり腿上げして次の一歩を出さないと雪に足がとられて前にコケる。時々太ももまで雪に埋もれて・・・。標高が下がって雪のない樹林帯に入っても、前の連中はスピードを落とさない。156㎝の私は「あんたたちの半分しか足の長さがないんやぞ」と悪態をつぶやきつつ、あっという間の下山。
今日は、車道に向かって一番近いルートで下りたので、車までの車道が遠い遠い。急峻な斜面につけられた車道から、法面(のりめん)をのぞいては、「ここなら下れるかなあ。今度は、ロープを持ってこようか。」と冗談半分で相談を始める小学生のような二人を軽く戒めつつ歩いた。
注】今回は、一番体力のない私にとって体力試しのような山行になりました。が、計画は、私より雪慣れしていない人を想定していました。その場合には、ワカンをきっちり使って、体力的にも余裕のあるスピードでの山行を実施したでしょう。体力的、時間的に無理があると判断すれば、途中引き返しの判断もあったでしょう。ここで、体力的技術的に自信のない方にひと言。
「私が参加したら予定の行程が行けなくて迷惑になるから、参加しないでおこう。」と思わないでください。山で遭難する大きな理由の一つに「慢心」があります。「ここまで来たから」「自分ならいけるはず」…この気持ちが怖い。
山で難しいのは、進む決断ではなく撤退する判断と決断。自分より体力の劣る仲間にあわせて動く決断が、体力のある者自身をも守ります。そして、声を大にして言いたい!
「途中で引き返した山行は失敗ではありません。」山は一歩入った時から日常とは異なる素敵な経験。引き返した山行には、順調に進んだ山行よりもはるかに有意義な勉強すべきポイントがあります。「いろんな体力の人が山を楽しむ」のが、山の会の醍醐味です。
わかんで遊ぼう!
UPDATE 2026-01-14
【日 程】 2026/01/11(日)
【参加者】 7名
【コース】 黒河林道P手前-東尾根-明王の禿ピストン
【記 者】 スエ子
もふもふの雪に私らのトレースつけて可愛いラッセルしたい。
大寒波初日、天気と相談し赤坂山は明王の禿と向かう。
青空の下少なめの重い雪を進む。
デビューの人も1年ぶりの人もわかん装着。久しぶりなもんで、装着の仕方が合ってるか心配……
カワイイ鹿さんうさぎさんの足跡をついてったり、うるさい枝を掻き分け道を選び先頭を交代しながら歩く。わかんは逆八の字にして歩いてね〜
暑い……お腹も減ったが止まると寒いし急登やし進む。
明王の禿が見えてきた。風も冷たく雪も締まって歩きよい。が、予報通り吹雪いてきた。
もうひと頑張り!美味しいとこ歩きたい!
皆で登頂!即下山!
赤坂山が…なんて今回はよろしいやん。
吹雪の中来た道を戻る。
すってんとお尻で滑った~
踏ん張るぞと思いながらもツルツルになったところをまた滑り~
笑った私もまた滑り~
トドメにおかまされて玉突き~
あ〜雪は楽しい!
追記)計画していた湖北の白倉岳を西から登るルートは北西の暴風が懸念されました。なので、登る山が風よけになってくれそうな湖西岸の赤坂山を東側から登るルートに変更。登っている頭上は青空だけど、目指す山頂から向こうは暗い空。案の定、明王の禿では暴風で油断すると吹き飛ばされそう! 急いで下山。少々雪が来たものの、風が防がれている分、みんなにも余裕が。かくて、大笑いの下山となったのでした。
きぬがさ山~猪子山で筋トレハイクin滋賀
UPDATE 2025-12-12
【日 程】 2025/12/07(日)
【参加者】 会員4名
【コース】 安土駅-桑実寺-観音寺城跡-観音正寺ーきぬがさ山ー地獄越ー猪子山ー北向岩屋十一面観音-能登川町
【記 者】 norokame
当初はきぬがさ山と安土城跡だったが、安土城跡の石段がかなり高い!と聞いてコースを北へとることに変更。
下山口に車をデポして、能登川駅まで歩き、電車で安土駅へ移動。駅前の看板を見ながらこれからのコースを確認し、田畑や住宅地をながめつつ桑実寺を目指す。覚悟はしていたが、いきなり階段が現れるが、山門がそこに見えホッとして登り出す。
山門に着くと見上げるほどの階段が果てしなく(私にはそう見えた)上へ上へと続いているではないか(ひぇ~)
仕方なくゆるゆると登り、途中の休憩所で一服しながら、やっと本堂へと登り着いた(ふ~っ)
まだ始まったばかりなのに先が思いやられるが、本堂にお参りして気を鎮めて次なる階段に挑戦。登り着いたところは観音寺城跡。日本最大の山城遺構だそうな。堅固な石垣が残っている。
少し下って観音正寺の裏手へ至る。西国32番札所だけあってたくさんの善男善女がお参りしている。私もその一人になって手を合わせ御朱印を頂く。
さあ、本日のメインコースへと舵を切り、きぬがさ山へとまた急な階段を登る。433mの山にしては登りがいがあった。山頂からは最後の山、猪子山がかなり向こうに見えている(まだまだやん)
気は焦るが足が焦ってくれない。丸太の階段を下ると地獄越という恐ろしい名前の峠に着く。行くも地獄、戻るも地獄なんだろうか?どんな地獄が待っているやら・・・行くしかないのでまた階段を登る。また下る、また登る・・・
雨乞い伝説のある雨宮龍神社を過ぎ、伊庭山、p4、p3、p2、p1と小さなピークを階段の上り下りを繰り返してやっと猪子山に到着(バンザイ!)時々「見晴らし良好」の立て札に導かれて展望を楽しむが、今日は少し霞んでいて琵琶湖も比良山系もぼんやりで残念・・・
最後にたどり着いたのは北向岩屋十一面観音のお堂。参拝してまた階段を下りるとデポした車がお出迎え。
このコース、4分の3位は階段だったような・・・でも、段差が大きくなくて歩きやすかったかも・・・
三つのお寺と一つの神社を巡り御利益はあるのかな???
編集者ひとり言:桑実寺の長い石段、お寺から先に続く長い階段。写真を撮っておけば良かったと後悔。あまりの迫力に登ることに集中しちゃいました。紅葉もきれいだったんですけどね。