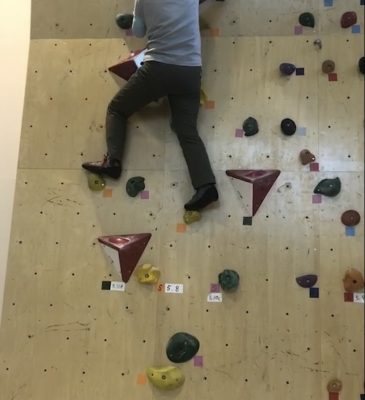【日 程】 2023/05/27(土)~2023/05/28(日)
【参加者】 会員7名
【コース】 1日目 長者原登山口-雨ヶ池-坊がつる-法華院温泉山小屋テント場-立中山-テント場
2日目 法華院温泉山小屋横テント場-雨ヶ池-長者原登山口…<車移動>… 由布岳正面登山口-マタエ(西峰と東峰の分岐)-西峰-東峰-正面登山口
【記 者】 Koume.S
九州の山。そういえばまだ登った事がない。私は、すぐに参加をぽちっと押しました。
金曜日の夜23時亀岡を出発。久しぶりに週末いい天気予報。 愛媛県三崎港に6時すぎに到着。着いてすぐにY師匠から、ザックの選び方やパッキング方法などのレクチャーを受けました。ザックのパッキングをやり直したり、背負ってみたり。みんな真剣です。
7時30分フェリー出発。8時40分大分県佐賀関到着。
車で長者原駐車場まで向かいます。くじゅう登山口を10時40分出発。長者原自然研究路の登山コースを歩き、木々の新緑に癒されながら、進みます。歩きながら、京都山岳連盟のフリーペーパーを下山される方に渡します。「京都から来ました。また京都トレイル来て下さい。」と声をかけながら。ソロですれ違った女性にミヤマキリシマの様子を聞くと、(計画していた大船山は、虫の食害でほぼダメだけれど) 立中山は、きれいに咲いているとの事。立中山に行き先変更。ミヤマキリシマに会いに行きましょう。
木道を歩き、雨ヶ池に到着。ミヤマキリシマが何ヶ所かピンクの鮮やかな色を付け、咲いています。登山道から坊がつるの広大な緑が見渡せ、遠くに色とりどりのテントが見えます。
13時前に坊がつるに到着。その南西にある法華院温泉山荘横のテント場に設営。荷物をデポして、立中山を目指して、出発。登り始めは、ムシの影響で、枯れていたものの、頂上付近は、鮮やかなピンクから薄いピンクが広がり、とてもきれいに咲いていました。
下山して、テントの中で、食事をすませ、法華院温泉で、汗を流し、湯の花の浮かんだ白いお湯で、疲れを癒します。
21時頃に就寝。早朝出発のため夜中の2時に起床。お湯を沸かして、朝ごはんの準備。夜中に食べるチキンラーメンは、美味しかった(笑)。テントを撤収し、3時頃に出発。 ヘッデンをつけて、途中暗闇に光る眼、夜中ずっと鳴き続ける鳥(トラツグミ)も気にしながら、足早に進みます。途中ようやく夜が明け、Y師匠が「早く歩けー。行くぞー」と喝をいれます。
長者原駐車場に5時30分到着。
由布岳までは、車で、40分ぐらい。途中コンビニで、食料を買い足し、正面登山口に到着。無料駐車場は、既にいっぱい。となりの駐車場に停め、6時30分頃、正面登山口よりスタート。
由布岳は、双耳の東峰、西峰の2つの岩峰「豊後富士」の愛称の山。
つづら折りの登山道をひたすら登り、緑の周りの山々の景色に癒されながら、進みます。
ようやく中央部のマタエ(鞍部)に到着。鎖のある西峰へは、Y師匠、H、Sの3人が登ります。献花の前で手を合わせ、緊張しながら、Y師匠の後に続きます。
岩は、持ちやすかったのですが、こんな高い所まで、岩にシャクトリムシがいて、3点支持をしながら、ムシを掴まないかヒヤヒヤ。
まわりは、ガスガスになり、景色は、残念ながら見えません。途中トラバースが1ヶ所あり、特に慎重に登ります。西峰1583メートルの頂上に着き、写真撮影。
足の置き場に気をつけて、鎖を使いながら、来た道を下ります。次は、全員で、東峰に登り、頂上でまた写真撮影。
それから、急いで下山します。つづら折りの登山道の長いこと。こんなに長かったっけって、いつもの下山あるあるです。
下山後、港までの途中、温泉により、さっぱりと汗を流した後、佐賀関港から愛媛県へ。関鯖やトリ天も食べたかったけど、時間が足りなくて、またの機会に。
帰りのSAで、お腹を満たして、瀬戸大橋経由で、京都、亀岡へ。往復で車1200キロ走行+フェリーの旅。皆さんお疲れ様でした。すごく欲張りな充実した山行になりました。
今回の山行でもたくさんの事を教えていただきました。 「安全に、楽に、楽しく登るために、必要なこと。末長く登山を続けて行くために…。」Y師匠より。